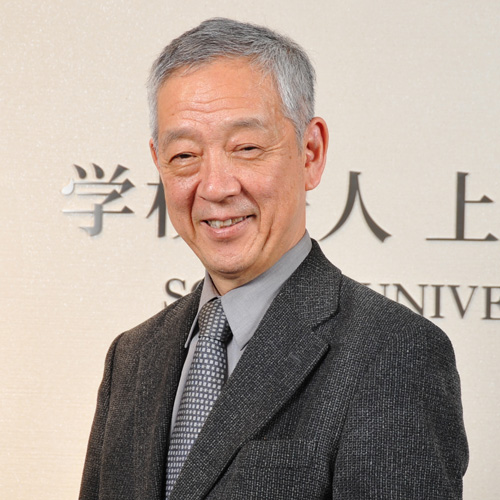
募集を終了いたしました。今後の開催予定のお知らせを希望する方は、資料請求(ダウンロード)フォームの【記入欄】に「講座(講師)名」と「開催予定希望」をご記入・送信ください。
宗教は、人間の生き方・考え方の根本に関わり、人類の精神文化に大きな影響を与えてきました。それゆえ「宗教とは何か」という問いは、あまりに大きく捉えどころが難しいものです。そんな大きな問いに向き合うとき、ひとつの手がかりとなるのは「救い」という言葉ではないでしょうか。
世界の三大宗教として知られる「キリスト教・イスラム教・仏教」は、「救い」を重視する意味で「救済宗教」と呼ばれています。苦難や苦しみに耐える力を与え、社会秩序の原理を提供し、精神文化の中核として、人類の文明化に大きく貢献してきました。
近代になるとこれらの伝統的な救済宗教が変化していくとともに、新たに多様な宗教集団が発生してきます。救済宗教の新たな形態の展開です。しかし、20世紀の後半から救済宗教にかわる新たなスピリチュアリティが人々の心をとらえるようにもなってきています。
本講座では、「救済宗教」を概観し、人間はなぜ「救い」を求めてきたのか、宗教による「救い」はどう変化してきたのか、現代人にとって「救い」とは何か、「救い」の後に来るものは何かを考えたいと思います。さらには、日本の神道やアニミズムの特徴を探り、日本人の宗教観を掘り下げてみたいと考えています。
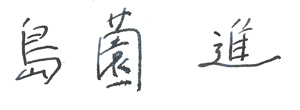
2回目以降は、事前に当日講義に関わるテーマについて各自の考え方・意見・講師に質問したいことを所定様式に記入し提出いただきます。提出物はクラス全体で共有し、さまざまな観点・経験からの感想を交わしながら学びます。
救済宗教は、人間の根本的な苦悩や限界を克服し、究極的な幸福・安寧・自由を実現すること=救済を、教義の中心に据える宗教とされています。特徴としては下記のようなものがあります。
・現世的な成功や平安を越えた、超越的な救いを志向
・普遍的な真理・道・教えへの帰依
・個人の内面の変容を重視
・来世・他界観・解脱・永遠の命などが教義に含まれることが多い
| 開催形態 | ハイブリッド開催(対面(キャンパス)、オンライン) |
|---|---|
| 日程 | 10/18、11/22、12/20、2026年1/17、2/28、3/28(すべて土曜日) 全6回 欠席時は録画映像の視聴が可能です。 |
| 時間 | 14:00-17:00(3時間) |
| 定員 | 25名 |
| 会場 | 慶應丸の内シティキャンパス/オンライン |
| 参加費 | 110,000円(税込) 割引制度・キャンセル規定 |
| お問い合わせ | 担当:柳 03-5220-3111 個別相談 資料請求 |
第1回 10月18日(土)14:00-17:00(3時間)
世界三大宗教といえば、キリスト教、イスラーム、仏教だが、これらは西暦紀元前五百年から紀元後千年の間に成立し、以後千年から二千年あまりにわたって、人類文明に大きな影響を及ぼしてきている。これら三大宗教の共通点は、永遠のいのちや安らぎにあたるような救いをもたらす生き方を教え、それは歴史上無比の偉大な教祖がもたらしたものと信じるという点にある。これら救済宗教がかくも大きな影響力をもったのはなぜか、考えていきたい。
第2回 11月22日(土)14:00-17:00(3時間)
今も救済宗教は大きな影響力を持っているが、そのあり方は近代と呼ばれてきた時代になって変化してきている。西洋ではカトリックに対してプロテスタント、日本では伝統仏教に対して新宗教が勢いを増してきた。そもそも救済宗教は帝国が展開するとともに世界に広まっていった。都市文明、書物の力が発展し、階級差が大きくなる時代に広がっていった。これに対して、近代世界では人々が平等だと感じられ、大衆参加が進む時代だ。この時代、宗教離れとともに救済宗教の大衆化も進んでいった。
第3回 12月20日(土)14:00-17:00(3時間)
仏教は僧侶と俗人、出家と在家、達人と一般人の間の相違が当然とされた宗教だった。少数者こそが悟りを得られるという形をとる。ところが、誰もが究極の良きあり方に値するという考えが広がり、大乗仏教が成立する。他者とともに生きる「菩薩」という修行者の像ができる。また、出家者が悟りを得ようとすることは仏法を世に具現することであり、世を仏法にふさわしいものにするという思想も当初からあった。衆生済度の教えと言えるが、日本ではその動きが顕著に見られた。
第4回 1月17日(土)14:00-17:00(3時間)
神道は日本独自の宗教形態だが、一方では地域社会の民俗宗教と重なり合っており、他方では仏教と習合し全国的な影響力を保ってきた。アニミズムにも通じる民俗宗教的な地域的な信仰が長く残ってきたのが日本の宗教文化の特徴の一つだが、それは、古代に天皇が担う神道信仰と神道儀礼を国家の精神的な柱にしようとしたことの影響が大きい。しかし、明治維新には神仏分離を行い、新たに国家神道を形成した。神仏習合と国家神道を捉えることが神道理解の鍵となる。
第5回 2月28日(土)14:00-17:00(3時間)
20世紀の後半になって、伝統的救済宗教に代わる精神文化を求める運動が世界的に広がってきている。これは近代化とともに力を強めてきた。唯物論的科学と近代合理主義の支配への失望とも関わっている。ヨーガや気功、東洋宗教から学ぼうとする動向、先住民文化の再発見、心理療法や神秘主義思想への関心などの動きだが、これらは「新しいスピリチュアリティ」として要約できる。また、新たなネットワーク型の霊性体験が尊ばれる動きでもある。救済宗教と「新しいスピリチュアリティ」の関係について考えていきたい。
第6回 3月28日(土)14:00-17:00(3時間)
現代においても救済宗教は人類の多くが帰依しているが、他方、救済宗教離れの動きも顕著に見られる。では、「救い」に対する関心は後退していくのだろうか。救済宗教の勢いが弱まっているように見える地域でも、救いへの関心が別の形で存続していると見ることもできる。「痛み」にはスピリチュアルな次元もあるという認識はその一つだ。「死」について、また「孤独」について、そしてどのように進む人々の孤立を超えていくかといった問題意識についても考えていきたい。
単発受講のお申し込みはこちら
今後の開催予定のお知らせを希望する方は資料請求(ダウンロード)フォームの【記入欄】に「講座(講師)名」と「開催予定希望」をご記入・送信ください。